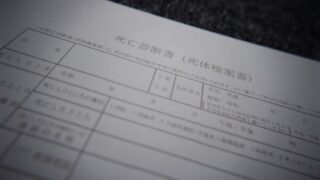その他
その他 <2025年>ありがとうございます!当ブログへ見にいらした皆様へ新年のご挨拶とご案内
2024年も多くの方々と共に歩むことができたこと、心より感謝申し上げます。現役火葬場職員である『火葬ディレクター™』として、2025年も火葬場や葬儀に関する役立つ情報をお届けしてまいります。年末年始の休場期間中は、今年も家族と過ごしながら心身をリフレッシュする予定ですが、ブログの更新はこれまで通り続けてまいりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。当ブログでは、皆様からのご意見やご質問を大切にしております。誤解や不足している点がありましたら、遠慮なくお知らせください。